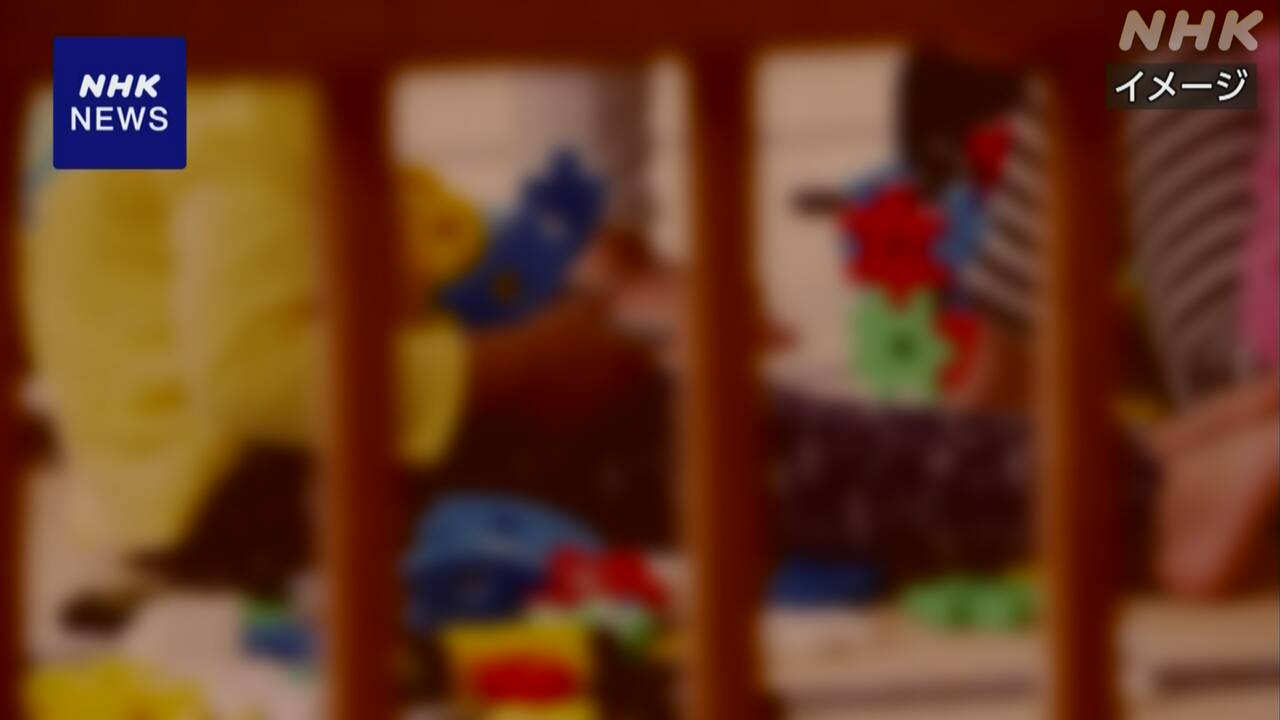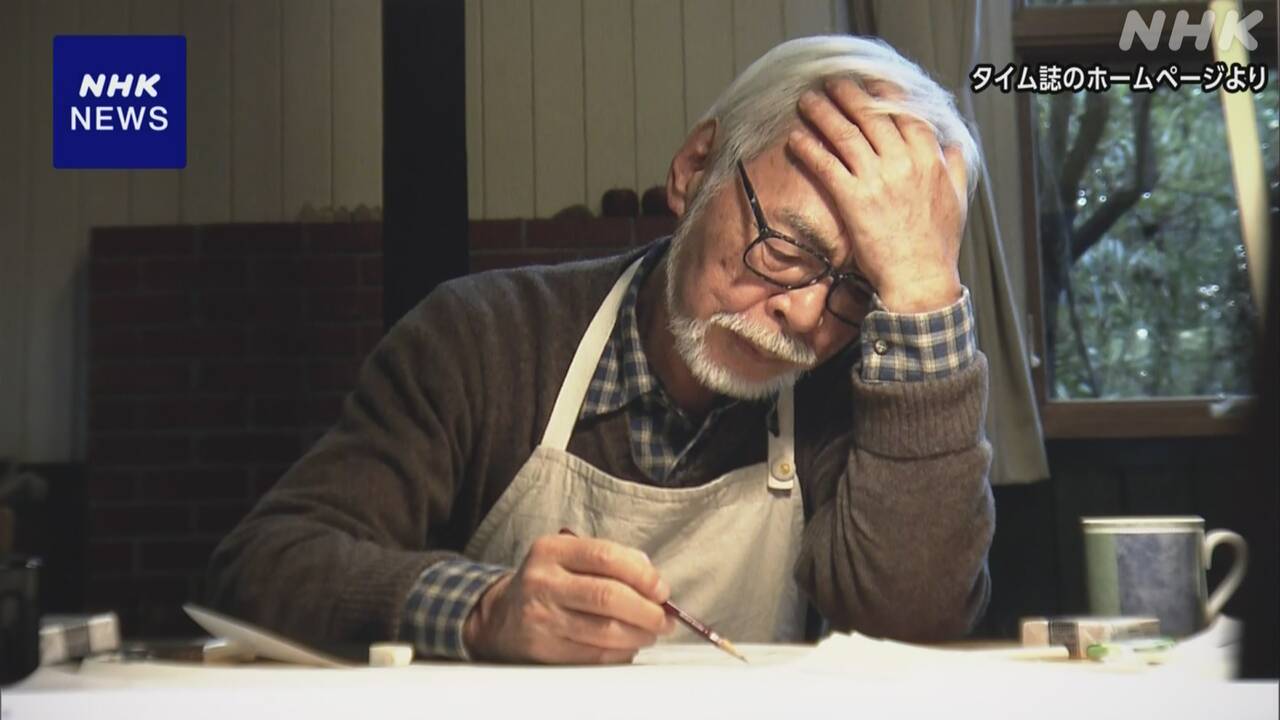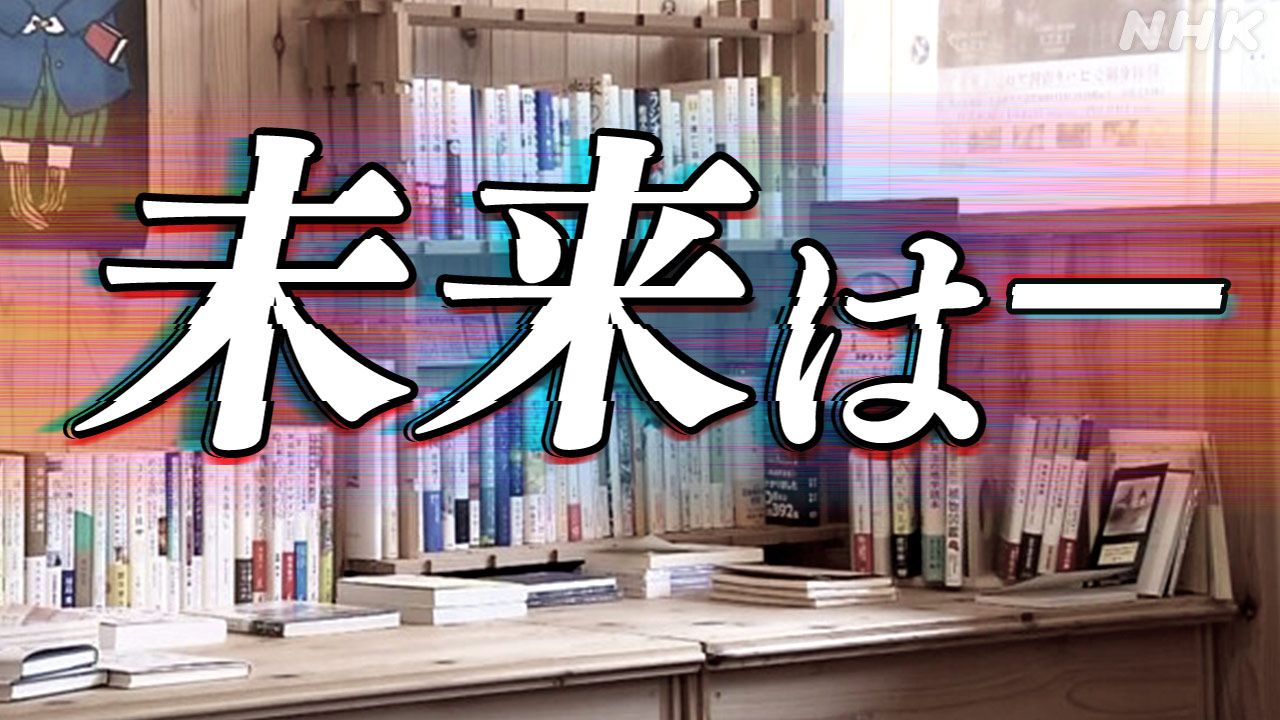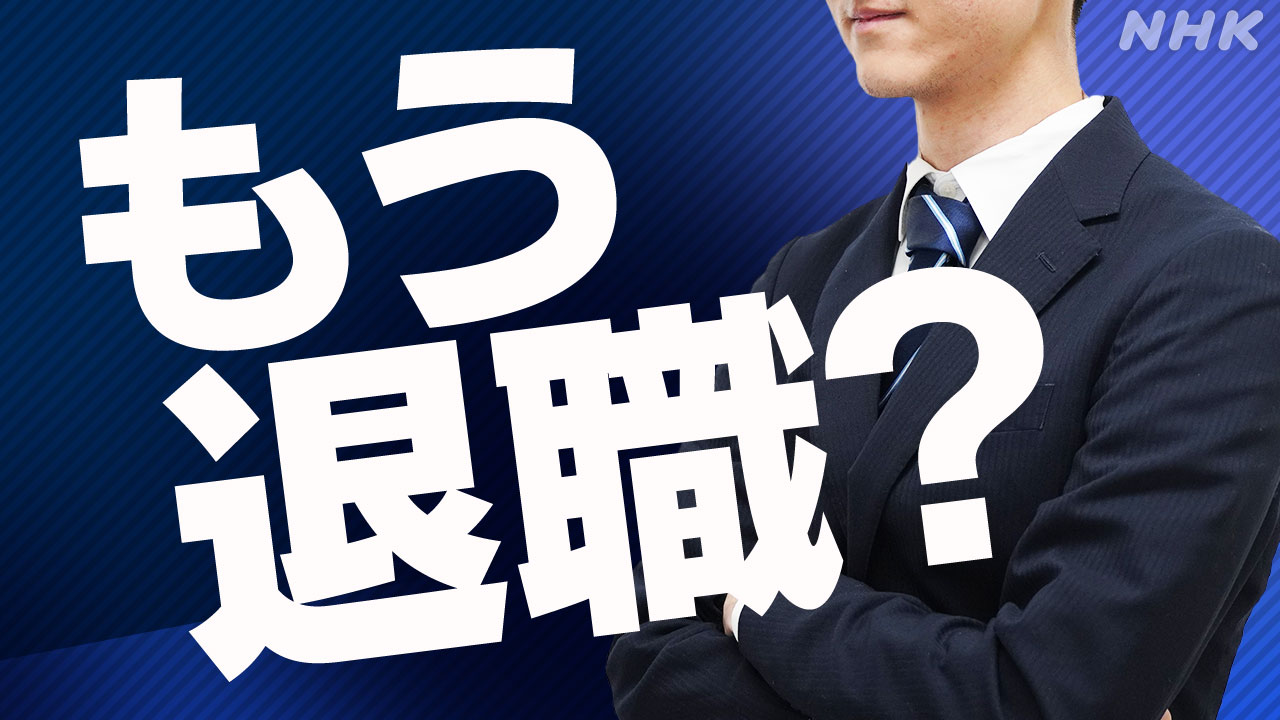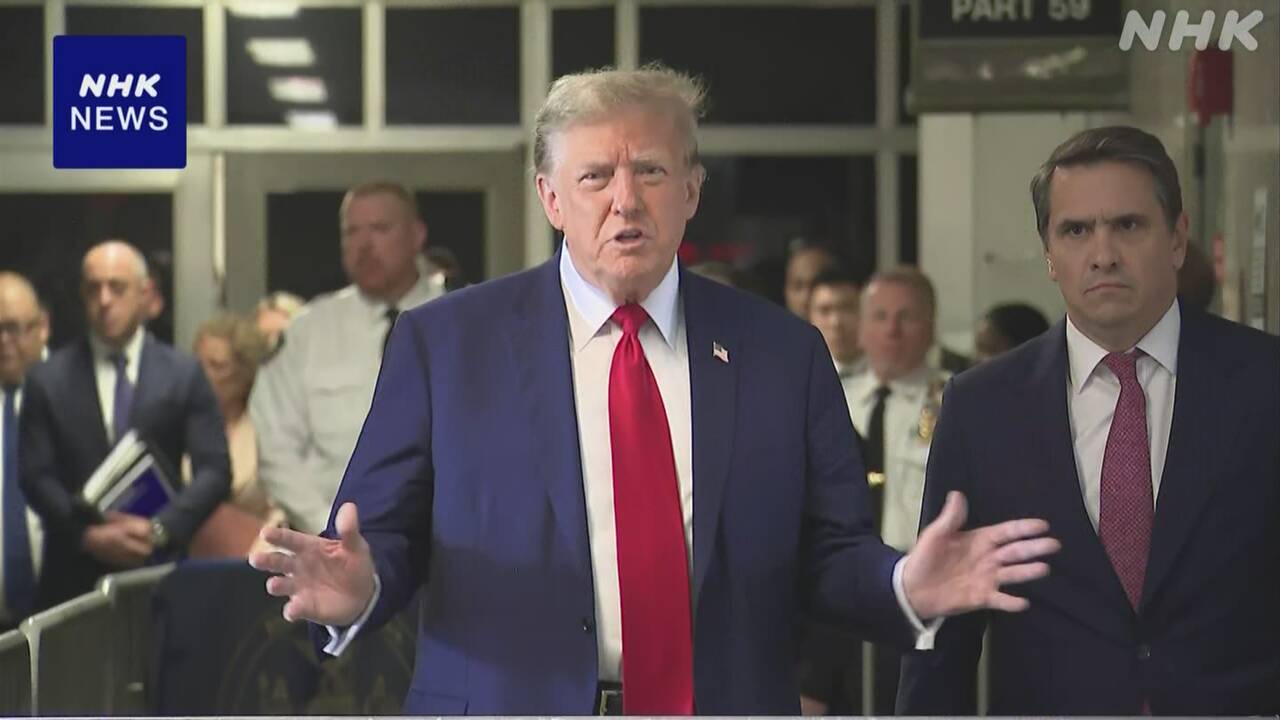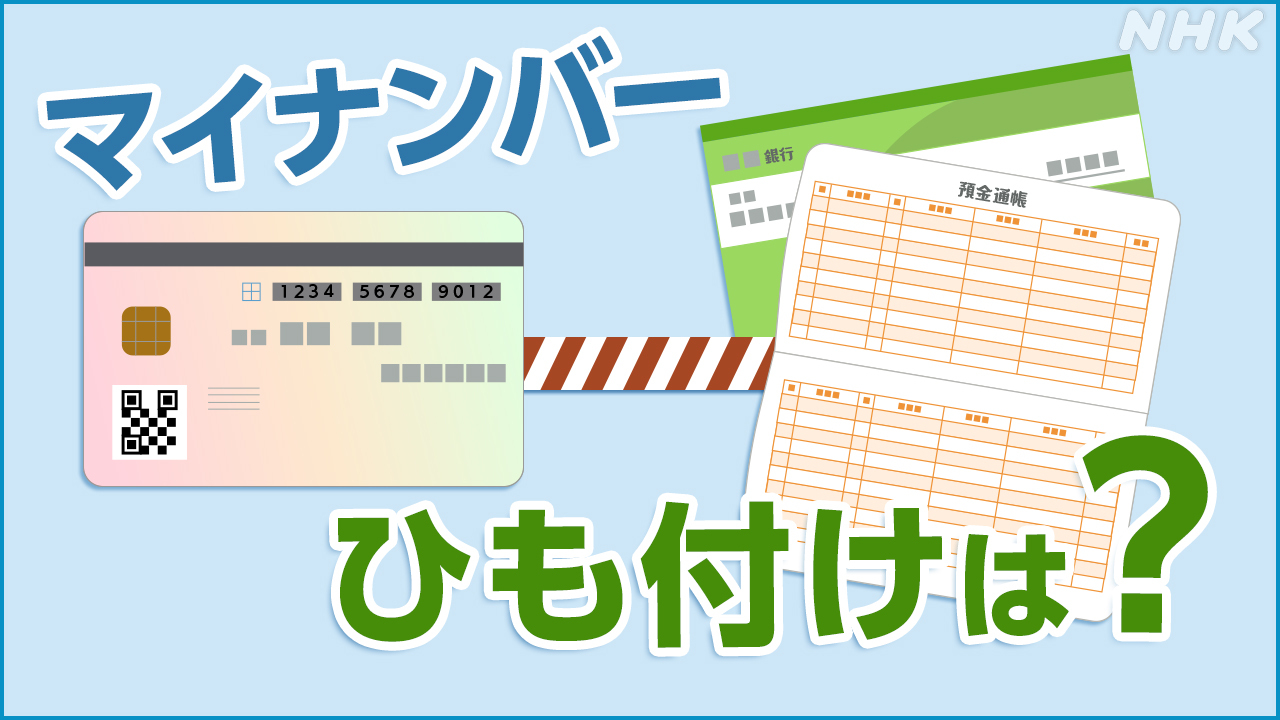ここが、あのふだんラジオをとっている?
(スー)
そうですね。はい、スタジオです。
(杉浦)
テレビに出られるのはかなり久しぶりで、あまり出られてないですよね?
(スー)
ふだんはそうですね。
(杉浦)
それはなぜなんでしょう?
(スー)
うーん…、あまり得意じゃない(笑)
なんかね、テレビって、やっぱり出たいっていう人のためのメディアだと思うんですよ。映像で伝えたいとか、自分の姿をもって伝えたいっていう人がやるメディアだと思ってて、私はそれがあまりなくて、なかなかね、こう「ワーッ」て楽しめないんですよね。
(杉浦)
今回はなぜ出ていただけることになったんでしょう?
(スー)
今回は杉浦さんが『OVER THE SUN』のリスナーだったっていうのもあるんですけど。
(杉浦)
はい(笑)
(スー)
ま、それは半分冗談で。10年目なんですよ、出版物を出して。いちばん最初の単行本を出したのが2013年なんで、10年目だし、ちょっといつもと違うことをチャレンジしようかなと思って。今回は。
(杉浦)
きょうはいろいろお話をうかがえればと思うんですが、「ジェーン・スーとは一体何者なのか」と、スーさん自身が聞かれたら何て答えますか?
(スー)
書いて、しゃべって、伝える人みたいな感じですかね。
(杉浦) もともとエッセイストになろうとか、ラジオパーソナリティーになろうっていうことが夢だったわけじゃないですよね? (スー) 35歳まで会社員をずっとやっていて、12、3年やってたんだと思うんですけど。ちょうどそのとき、SNSの「mixi」がはやっていて。そこでジェーン・スーっていう名前でやってたんですけど、そのSNSに「コミュニティ」っていうのがあって、そこで自分やお友達と一緒に作ったものに人が結構集まってきて。 それを見た人から「このコミュニティで書いてることを雑誌に連載しませんか?」とか、「何か書いてみませんか?」とか、そういうオファーをちょこちょこっといただいたりして。ちょうど会社員もやめてそんなに忙しくなかったんで、「じゃあ」なんて言って。まあ、小遣い稼ぎですよね。それで書き始めたり。 ラジオに関しては、先に作詞なんですよ。もともと音楽業界、レコード会社にいたんですけど、そこを辞めてしばらくしたときに、元同僚が立ち上げた会社があって、「アイドルのプロデュースをやるから一緒にやらないか?」ってお誘いいただいて。資料を作ったりとか、衣装考えたりとか、そういうことは前の仕事でもやってたんで、「やります、やります」「ありがとう」って。 それもアルバイトと言っていいのかしら、なんか本業ではないんですけど、自分が役に立てるなって感じでやってたんですよ。そしたら「作詞も」って言われて、「いや、作詞はちょっと違うんじゃないの?」って言ったんですけど、それがすごく大きな自分の分岐点ではあって。 信用している人から「やってみて。やってみたらいいよ。できるよ。」って言われたものはやってみようと思って、そのとき初めてやったんですよ。そのときの同僚は、仕事の実績もやり方も尊敬するものがすごくあったので、彼が言うならじゃあ、興味もないし技術もないけどやってみようかなと思って、やったら意外と楽しくて。 それをきっかけにラジオに出るようになって、これも、しゃべることに興味があったわけではないんですけど、プロデューサーの方が仕事もすごくおもしろいものをやってらっしゃるし、人としても信頼しているから、「じゃあ、その船に乗ってみようかな」って。 信頼する人のことばを信じて、船をそのつど乗り換えていってここに来たって感じですね。 (杉浦) スーさんの時代は、まだ一つの会社でずーっと仕事をするのが普通だった時代だと思うんですよ。それでも組織を離れてみたり、来た船に乗ってみるっていう感覚になるのって、自由で羨ましいなってすごく思うんですけど。 (スー) 自分も気がつかなかったですけど、意外と飽きっぽいのと、嫌だなって思うといなくなっちゃったり、あっちがやりたいなと思うといなくなっちゃったりっていうのを意外とやるたちなんだなと思って。 あとはやっぱり、自分が「つまらないな」とか「もっとほかにやりたいことがあるな」っていうふうに思ってるのに、そっちのほうに自分を動かさないでいい理由って100でも200でも思いつくじゃないですか。「今仕事が忙しい」とか、いろんな事情があるって言って。「もうちょっと機が満ちたら」とか、「いい仕事が見つかったら」とか。 だけど、何か機が満ちたことってないなと思って。だったらもう話をもらった時点で。それは転職のときにいちばん思ったのかな。「準備ができてることなんか絶対ないんだな」と思って。おもしろい話が来たとき、やってみたいことができたときに、自分が準備万端ってことはたぶんこの先も一生ないだろうなと思ったので、それでやり始めたら、どんどん次から次へと移っていくようになっちゃって、ですね。
(杉浦) 2020年にポッドキャストの『OVER THE SUN』が始まって、この配信で一気にリスナーの層が拡大したなという印象があります。 (スー) そうですね。ラジオをやってるときは、朝、おばあさまとかに「あら、これから行くの?頑張ってね」なんて話かけられたりすることはあったんですけど、ほとんどの人が気付かない。唯一気付くのがタクシーの運転手さん。声で分かるんで。顔じゃなくて。 (杉浦) 聴いてるから、ラジオ。 (スー) そうなんです。声で「もしかして…」っていうことはあったんですけど。 それがポッドキャストが始まったら、若い人にすごい声かけられるんですよ。それがびっくりで。表参道とかを歩いていて「ジェーン・スーさんですか?」、渋谷を歩いていて「ジェーン・スーさんですか?」って、新宿の、銀座の、いわゆるおしゃれな場所っていうところをたまに私も通ることがあるんですけど、そういうところで声をかけられて。しかも20代後半とか30代前半の方に。 「何でこの人たちが聴いてるんだろう?おばさんのための番組なのに」と思いながら、まあ、楽しんでもらえるんだったらいいかと思ってるんですけど。変わりましたね、そういう意味では。 (杉浦) そうやってリスナーの層が広がっていっていることに関してはいかがですか? (スー) ありがたいですね。ポッドキャストだからなんだろうなと思います。なかなかラジオをスマートフォンで聴けるっていうことをまだ知らない若い方たちもたくさんいるし。でもなぜかね、ポッドキャストは伝播(でんぱ)しやすいんですよね。女性の「クチコミ」の力っていうのを久しぶりに実感しましたね。頼もしいと思って。 おいしいものとかすぐ知らせるじゃないですか。サプリとか、意外とコスパがいい化粧品とか、そういうの回ってくるじゃないですか。たぶんそれと同じ。そこの輪には入れたんだなとは思いますけど。
でも、いってみれば、『OVER THE SUN』って堀井美香さんとのおしゃべりで展開されていく番組で、あえて言うなら、無駄話…? (スー) そうですね。どう考えても無駄話です。あえて言わなくても完全に中身ゼロです。 何かを伝えようとか、誰かを救おうとか、そういったことは一切考えてなくて、堀井さんと私、週に1回、気心知れた女友達と会ってしゃべる時間を大切に、と思ってますね。 それぐらいの緩さがもしかしたら気に入ってもらえてるのかな。そんな感じもします。 (杉浦) 確かに、放送っていうとちょっと身構えたり、テレビは特に身構えてしまう部分もあると思いますけど、なんかこう身構えてる様子が二人になくて。 (スー) ないですね。まるでないですね。 (杉浦) でも二人の私的な、プライベートに近い会話をしゃべるっていうことに抵抗とかはなかったんですか? (スー) 特になかったかもしれない。聞かれてみて初めて気が付きましたけど。 (杉浦) それは受け入れてもらえるだろうっていう感覚もあったんですか? (スー) 「同じような話をしている同世代の女性はたくさんいるはずだ、なぜなら私が、なぜなら堀井さんが、お互いそれぞれ別の場所で同じようなことしているから。」と考えるならば、何をやろうとしているか、何を楽しんでいるのかは、何をしゃべっても伝わるだろうなとは思ってましたけど。「ちょっとお邪魔しまーす」って言って友達のうちに来るような感じで聞いてくださってる方が多いんじゃないかな。 みんな同じ土俵で楽しんでくれるのがうれしいです。何か私たちをジャッジするでも、あがめたてまつったり、さげすんだりとかではなくて、ほんとにみんな同じ草原で、「来た、来た!遊ぼうよ、金曜日だよ、始まるよ!」っていうスタンスで聴いてくださってるのが分かって、それがすごくうれしいし、楽ですね。気が楽です。 (杉浦) 2人の会話、2人のおしゃべりを聞いているだけなんですけれど、なんだか聞いている側も3人目として参加しているような感覚になるんですよね。 (スー) 思い当たる節があったりするようですね、聴いてくださってる方にも。 それでクスっと笑ったり、一緒に怒ったり、たぎったり。そう考えると、3人目がたくさん世界中にいると思うと心強いですよね。 (杉浦) おしゃべり、まあ、無駄話なんだけれど、なぜか人生のいろんなことに通底するような、通じるような、最終的にはまとまっていくし、まとまらないときももちろんあるんですけど、それがすごく不思議だなって思っていて。 (スー) でも、ああやって、何でもいい話で分かった気になるのは、おばさんの特徴ですよ。 (杉浦) (爆笑) (スー) 「分かる」「いいね」「そうよねー」って言って、自分たちで「いいこと導き出した」みたいなこと言って終わって、「じゃあ」って言って帰っていくのは、もう中高年女性の特権だと思ってますから。私たちは。で、みんなで「分かる」「そうよ」「いいこと言う」ってお互いに言い合ってるっていうのが楽しいんですよ。 (杉浦) なるほど(笑) (スー) たぶん聞いたことのない人は、全く番組の概要がつかめないと思うんですよ。「『OVER THE SUN』って何ですか?」って聞かれて「中年女性2人の無駄話です」って言われたら、そこに時間を割く理由ってないじゃないですか。でも、実際に経験していただいて、何か自分の生活に変化が起こるっていうことがあるんだとすれば、そういう意味ではスパイスみたいにはなってるのかもしれないですね。 SNSなんか見てると、「きょう、会社ですっごい嫌なことがあったけど、帰り道に聞いたらゲラゲラ笑って、もう気持ちが晴れちゃった」とか、「子どもの寝かしつけしているときに聞くと、笑っちゃって子どもを起こしちゃって大変」とか、「くだらない話だと思ったらすごい自分に刺さる話をされて、いろいろ考えなきゃ大変」とか、そういう何かちょっとこう、ちょっと日常を動かしたり、矛先を変えたりっていうものに、無駄話っていうものが役に立つんじゃないですかね。うん。
「負けへんで」 実は、ポッドキャストの2回目の配信のときに登場していました。
番組の中で、「パワーワード」と言われるような強く印象に残ることばがいろいろな形で出てきますけど、その中でもやはりいちばんにあげられるのが、「勝ちにはいかないけど、負けへんで」っていう言葉だと思うんです。 あの言葉はどういう思いで発している言葉なんですか? (スー) あれはどういう流れで出てきたのかもそんなに覚えてないですけど、「そんなにガツガツいくほど強くないです」っていうような言葉を女性から聞くことが多くて。「私はそんなに強くいきたくないし、いけないし」っていう。 それで全然いいんじゃないのかなと思って。人それぞれの出力ってあるじゃないですか。でも、それって、力が強い人に負けちゃうってことじゃなくて、勝ちにいくっていう闘争心がなくても、負けないっていう気持ちは持ってたほうが明日につながるなと思って、私は…。 それがたぶんポロッと出たんですけど、意外とみんなに大事にしてもらっててうれしいですね、その言葉を。 (杉浦) 今みんな合言葉のように、「負けへんで」…。 (スー) いやもう、ほんとに、「負けへんで」ですよ。 立ち上がれば負けてないですから。 (杉浦) あー、立ち上がれば負けていない。 そっか。立ち上がればいいんですね、とにかく… (スー) そうです。 倒されるかどうかじゃなくて、立ち上がるかどうかですから。
スーさんの番組のリスナーにその魅力を聞いてみると、「すごく共感してくれてるなっていうのが伝わってくる」「『育児中の方、お仕事中の方、お休みの方』って言われると、なんか『ああ、私もいていいんだな』みたいに思いますね。ラジオだから、そばにいるような気がしちゃいますよね。」と、スーさんが寄り添ってくれる存在であることを魅力としてあげる人がいます。 そして、「言葉のチョイスがすばらしいっていうか、私には思いつかないような言葉をいつも使ってらっしゃるので膝(ひざ)を打つことがすごく多い」と、スーさんの発する言葉の魅力を語る人が目立ちます。
リスナーの方にスーさんの魅力を聞いてみると、いろんな方が言っていたのが「言語化してくれる」っていうことでした。スーさんが言語化してくれるから、そこからまたいろんなことを考えたり、いろんなきっかけを起こせたりすることができるっていう。 言語化についてはどう考えていますか? (スー) 言語化することが自分で得意だと思ったことはないんですけど、まあ皆さんがそうおっしゃってくれるってことは、たぶんそこが私の特徴の一つなんだなと思ってて。 じゃあ、何でそうなったかっていうと、モヤモヤすることってあるじゃないですか、うまく言葉にできないモヤモヤしていること。 (杉浦) あります、あります。 (スー) それをすごい考えて、考えて、友達とウワーッと話して、「どういうことなんだ? ああいうことなんだ?」ってウワーッと話して、「分かった!」ってなるのがすごい好きなんですよ。 (杉浦) あー! (スー) この「分かった!」のために生きてると言っても過言ではないぐらいこの瞬間が好きで。その「分かった!」を電波にのせたり、文字にしたり、文章にしたり、なんじゃないかな。 (杉浦) 昔からそういう行動をされてた…? (スー) そうです。 「はぁー、これ、そういう意味だったのか!だからモヤモヤするんだ」とか、「だから、これ、なんか自分がうまくできなかったんだ」って。 言語化って皆さん言うんですけど、言語化というよりも、モヤモヤしていることの理由を突き止めて、自分の中で「腹落ち」させる瞬間が何より好きなんですよ。それが楽しくてしょうがない。 (杉浦) 楽しくてしょうがない、スッキリするとどういう気持ちになるんですか? (スー) おいしいごはんを食べたあとぐらいの満足感はありますね。 (杉浦) でも、確かにそのモヤモヤした気持ちに言語化…、何か言葉が付くと、次の展開も考えられるかもしれないですよね。次に何を行動するかとか。 (スー) そうですね。自分のボトルネックがどこにあるかって自分一人で考えてると分らないんですよ。 でも、人と話すと結構気づけることがあるので、だから私はよく「人と話したほうがいいよ」って言うんですけど、あと書き出すとかね。 とにかく自分の中から出すっていうことが何より大事だと思ってて、それをすることで進めていけるコマって確実にあるので、私の体感上は。 (杉浦) そのモヤモヤは、すっきりすればいいんですか?解決しなくていいんでしょうか? (スー) まずはすっきりさせることで、世の中の見え方がかなり変わるので、そこからですね。 そこから勝手に話が動きだすので。今までずっと止まってたと思ってたものが、硬直してたものが動きだすので、そこから先その指針を持ってると自動的に、「これは解決できることだ」とか、「これはちょっと解決に時間がかかることだ」とか、「なるほど、こうやって取り組んでいこう」とか、自分の態度が決まりますよね。 それがモヤモヤしたままで何がなんだか分からないと、どうしていいか分かんないじゃないですか。モヤモヤの霧が晴れれば、それに対して自分がどうするか決めやすくなるから、あんまりすぐ解決っていうとこまでいかないかな。 (杉浦) そこからは、自分の力っていうことなんですかね? (スー) そうですね。そうですね。 で、力はあるんですよ、誰にでも。誰にでもっていうと、また語弊があるというか、それを私が決められることではないので。ただ「あなたにその力がないって誰が決めた?たぶんあなた自身じゃないの?」っていうことは、問うていきたいですね。
スーさんの中で言葉を発するっていうことは、どういうふうに意識されてますか? (スー) ラジオの仕事を始めてかなり変わったと思います。 昔、仕事をする前はもっと短絡的でしたし、自分の半径5メートルにしか人はいないと思ってたと言っても過言ではないような表現を使っていたこともあります。ただ、ラジオをやることで、それが電波にのって遠くまで、見知らぬ人の耳にまで届く経験をしていくうちに、それぞれの生活や事情に思いをはせられるようになったのかなあ…。 書く仕事だけではたぶんそうならなかったと思います。 (杉浦) 言葉を投げかけるときに何かこういうことはしないようにしようとか、意識していることってありますか? (スー) ズバッと言い切るとか、何かの現象を斬るっていうようなことはしないようにしていますね。 (杉浦) でも答えを、簡単に答えを欲しがるっていう人たちって結構いると思うんですよね。それについてはどう思いますか? (スー) 「こちらのお店では扱っておりません」ってお断りするだけですよ、私は。 (杉浦) (笑) (スー) 「ちょっと在庫置いてないんですよね、うちは」っていう。 例えば、私のラジオを聴いてくださってる方、ポッドキャストを楽しんでくださってる方、本を読んでくださってる方が、私の創作物が何かを考えるきっかけになったらいいなと思ってるんです。でも、私の創作物なり発言なりが思考停止のお手伝いをしちゃうのがすごくいやなので…。 ズバッと斬る言葉が出てくると気持ちがいいじゃないですか。で、そういうものを私も欲しがるし。でもそれをやると、その人が自分の力で考えるっていうことをしなくなると思うんですね。そうすると、何かを享受しているつもりで、実は奪われてるってことになるので、そこに加担したくないのかもしれないですね。 人の言葉って強いとまねしたくなるじゃないですか? (杉浦) はい。 (スー) で、それをそのまま使いたくなるじゃないですか? (杉浦) はい。 (スー) SNSの恩恵と…まあ、功罪もあるんでしょうね。功罪というか、それが罪のほうになるのか人によって判断は異なると思うんですけど。強い言葉を使ったり、ズバッと耳心地のいい言葉を使ったりすることで、それをまねして使って、本当にその人の心の底からそう思ったのかとか、「腹落ち」したのかっていうのが分からないような言葉が氾濫しているように思うんですよね。 それを見たときに、「ああ、ここに加担するのは、何かを提供しているようで奪ってるだけだからよくないな」と思って。そこは気を付けているところかもしれないです。 だから「背中を押してください」とか言われると、「押しません」って。
(スー) 私は本当に人生の後悔が少ないほう、大体のことは後悔していないんですけど、唯一あるとしたら、もう少し早めに自分のこと信用してあげればよかったかなと思います。 (杉浦) どういうことですか? (スー) 例えば書く仕事をしたり、しゃべる仕事をしたり、興味はなかったとしても、何か若いときに気軽にやってみるチャンスってたぶんあったと思うんですよ。でも、そういうところで手を挙げなかったし、やっぱり「私なんかが」と。 私が自分でおもしろいと思ってることを人はおもしろいと思わないだろうなと思ってたので、もう少し自分のやりたいとか聞いてほしい、やってみたいっていうものに飛びついてもよかったなと思ってて。 じゃあ、どうやったら飛びつけるんだろうって考えるとやっぱり、自分のことをもう少し信頼してあげるっていうことしかないと思うんですよね。 (杉浦) 自分のこと信頼するって、確かにできるようでできないことですよね。 (スー) 自分のことがいちばん信用できないっていうのが一つの真理じゃないですか。自分のことをいちばん信用できないっていうのと、自分のことを信じてあげるって、実は同時に成立できるんですよね。 私はこういう怠け癖がある、こういう失敗をする、こういうときに気付いちゃう、だから何でも信用できるわけじゃないぞ、でも次のチャンスにはできるかもしれない、このあとひっくり返せるかもしれない、っていうふうに信じる。でも、100%信用しないっていう。 この二つが自然に同時成立できるようになったのはやっぱり40過ぎてからだと思うんで、もう少し手前にそれができてたら、もっと遠いとこにいけることもあったのかなと思いますね。
若いときに、今ほど「女性とは」っていうことを問われずに青春時代を過ごしているんですね。 今の若い女性なんかは、「女とは」っていうことをもっと考える機会がたくさんあると思うんですけど、私の場合ぼんやりしてたのもあって。 大人になって、つまり社会人になってみて、「なんかおかしいぞ」とか、「なんだろう、これ」って思うときに、結構な確率で、「これ、私が女だからだ」って思うことがあって。たぶん同じことが男性にもあるはずなんですよ。「なんか苦しいぞ、なんかおかしいぞ。ああ、これ、俺が男だからだ」っていうこともあると思うんです。 それを因数分解して、「こういう構成要素になってるのか」っていうのを見るのがやっぱり楽しくて。やってるうちに、「ああ、これ、自分のせいだと思ってるけど違ったじゃん。」「ねえねえ、これ、自分のせいだと思ったけど、私、違ったよ」っていうのを書く、しゃべる、っていうことをしているうちに、たぶん人がたくさん集まってきてくださったんだと思うんですけど。 だから、女性のありようを問うとか語るとかっていうつもりはなくて、あくまで私事、自分の事として考えたときにどうしても女性であるっていうタグが自分についてくるので。それについていろいろ考えてたら、女の人の成功譚(たん)がやっぱり圧倒的に少ないんですよね。 昭和40年代、50年代生まれぐらいかな、その世代の私たちが小学生だったとき、図書館にあったのって、キュリー夫人、ナイチンゲール、ヘレン・ケラー、マザー・テレサ、この辺りですよね? 実際に彼女たちが何をしたかっていうことよりも、やっぱ献身とか、自己犠牲とか、あとは苦しくても我慢をするとか、そういうことが尊ばれる。 なんとなくそういうことができるほうが尊い、女性として価値が高いっていうようなものを、たぶんうっすらぼんやり私は自分でインストールしてたと思うんですよ。それによって、自分なんかがって思うときもあったし、自分自身を信じられなかったときもあったし、そうできない自分を責めたこともあったし。 でも、「あれ?おかしいぞ。」「別にそうじゃなくても、生きるすべなんてたくさんあるじゃない」って言ったときに、「じゃあ、どんな人がいるの?」っていう女性の成功譚が、男性よりやっぱり圧倒的に少ないんですよね。あったとしても尽くし系とか、自己犠牲系とかが多くて。そうじゃない、自分の居場所を自分でつくった人の話が聞きたいなと思って。それで、13人の方にお話を伺って、本にしたんですよ。 私が子どものころ、女性の駅員さんっていなかったんですよね。 (杉浦) ああ、私が子どものころも、まだそんなに多くなかったと思います。はい。 (スー) で、女性の駅員がいないのは、できないからだと思ってたんです、私は。やっちゃいけないとか、できないとか、そういう理由だと思ってたんです。 でも、大人になって、そこにそういう人たちがたくさん、当たり前のように目にするようになれば、「なんで私、あんなこと思ってたんだろう」って今になると思うわけですよ。 テレビで見てるあの俳優さん、あのタレントさん、スタイリストの人、美容家の人、特別なんじゃなくて、誰も最初から自分の席を用意されてた人はいなくて、みんな自分でその居場所をつくってった。女性の場合は、やっぱりまだまだ座る席がそもそも用意されてないってことがすごく多いんで、自分で居場所を作んなくちゃいけないと思うんですよ。 それで、読むことによって、もしかしたら自分もこっち側に行けるのかも、これがやってみたいのかもって思ってもらえたらうれしいな。見たことがないから、自分にはできない。あれは特別と思ってるだけで、たくさん見れば当たり前のようになってく。それを当たり前のものとして次の世代に渡すっていうのが、もしかして女の仕事なのかなと思ってて。 「そんなもの私たちの手に入るわけないわよ、あれは特別よ」「あれは、ほかの人たちのものよ」って言ってたものを、公平にして、自分たちの手元に獲得をして、そして、あるのが当たり前っていう状態で次の世代に渡していくっていうことに、少し「いっちょかみ」できたらうれしいなと思ってます。 (杉浦) 今お話聞いてて思ったのは、それこそスーさん自身もご自身でいろんな来た船に乗って、で、今のこの位置があるんだと思うんですけど、スーさん自身がまさにその位置を勝ち取ったんじゃないかなって気がするんですけど。 (スー) 勝ち取ったっていうと、不断の努力があったように聞こえるかもしれないんですけど、私の場合は、本当に運も縁もよかったし、あと、たまたまはまったって感じかな。 目の前のことをこつこつやってれば、はまるときって来ると思うんですよね。いろいろ自分の中で、生きてきて自分の法則みたいなのが分かってきたんですよ。で、何か話を来たときに100%準備ができてることはまずないとか、どこに行くのか分かんなくても、いただいた仕事を120から200ぐらいの間で相手の期待を超えるものを返していけば、いい方向に扉は開いてくとか、そういうのは、この年齢になって分かってきたことかもしれないですね。 (杉浦) 自分の法則って、いいことばですね。 (スー) 誰にでも当てはまるわけではないんですけど、私の法則は、少しずつ見えてきたと思います。 それで、その13人の女性に話を聞いて、皆さん全部違う話をするし、活躍している場も全部違うし、時代も全部違うのに、読むと通底しているものがやっぱりあるんですよね。それが私はほんと鳥肌立つぐらい役得だなと思って、うれしくて。全部話を聞いた私しか、最初は知らないから。こういうことを知る瞬間のために生きているなと思いましたね。 みんな違う話をしているのに、みんなおんなじ話をしているってことは、ここにも何らかの法則があるんだとか。 (杉浦) あれはなんでなんだろう、確かに多種多様な女性たちで、年齢も幅広いですし。あの13人だけじゃなくてもこの通底するものって、何なんですかね? (スー) それをひと言でずばって言っていくと、だんだん消費されていって、みんな考えなくなってくんですよ(笑) (杉浦) ああ、確かに。 (スー) もっと長い期間で、例えば「この人はこういう話をした」みたいなことをたくさん話して、その流れで、私が感じた彼女たちの法則はこうですっていうお話をするのと、「成功した13人の女性に聞きました。共通する法則はこれ、これ、これ」ってやるのだと、入り方も違うし、理解力も違う。でも、ズバンってもらったときの喜びみたいなものは、そうやってパワーワードで切っていったほうがあるんですよね。 (杉浦) 快感ですよね。 (スー) そうです、そうです。 (杉浦) でも、それをしちゃいけない。
10年、物を書いて分かったんですけど、女の人が元気だとうれしいんですよ。私が楽しいんです。女の人がすごい笑顔で元気で楽しいと、私もすごくうれしいし、楽しいし、そういうものが見たいし。で、それに呼応して男の人たちの中で、いわゆるザ・権力側っていうのではない人たちが、自分自身を解放したりとかっていうところに派生的につながってくんだったら、もうそれはほんとにうれしいことこの上なくて。 でも、まず最初は、やっぱり女の人が自分を好きでいて、自分を楽しんでる様子を見るのが好きなんだなと思って、そういうものと近いところにあるものを書きたいっていうのはありますね。 (杉浦) どうしたら自分が幸せで、みんなも幸せな生活が送れるんだろうか、そのためにはなにが必要なんですか? (スー) 今はただ、正解がないんですよ。だから、それで一番難しいんだと思います。 (杉浦) 正解がない? (スー) 多様性が担保されたってことは、つまり正解が一つじゃなくなったっていうことなんで。 多様性がある社会、私もそのほうがいいと思います。っていうことは、つまり人それぞれの幸せのゴールが違う、それは正解が一つじゃないってことなんです。だから、自分がどこを目指していいか分からない。 よくロールモデルがいないって言われますけど、女の人のロールモデルなんて簡単に見つかるわけなくて、だって「仕事してる、してない」、「子どもいる、いない」、「結婚してる、してない」で、ライフステージが変わってきますから、女性は。その2×2×2で、最低でも8パターンあるわけじゃないですか。一人の人をロールモデルにするのが難しいと思うんですよ。 そう考えるんであれば、自分の中の正解っていうのを自分で探し当てなきゃいけないっていうのって、ものすごく胆力がいるし、基礎体力もいることなんですね。だって、誰かが言ってる正解を追いかけていったほうが楽なんだもん。「この歳でだいたい結婚して、子どもいて、マイホーム買って、こういう仕事をして勤め上げて」っていうロールモデルというか、正解だったわけじゃないですか、それが。でも、正解がないから、どうしていいか分からない。そりゃ生きづらいですよね。 (スー) 失敗しても、もう一度立ち上がって、もう一回トライもできるんだよっていうことは言いたいんですよ。一生懸命頑張ったこと、自分としては諦めたくないことで失敗しちゃった、うまくできなかったってことには、「じゃあ、もう一回チャレンジしてみなよ」っていうことは言える。だから、「失敗してこい」じゃなくて、失敗しちゃったっていう人に「じゃあ、何とかもう一回立ち上がる方法、一緒に考えようか」っていうのは言いたいかな。 (杉浦) そういう社会の中で生きていて、やはり『OVER THE SUN』聞いて、最初に「よくぞ、よくぞここまでたどりつきました、お疲れさま」って、冒頭で言われると、すっと肩の力が下りるというか、そういう感覚がすごくあって。 (スー) ありがたいです。金曜日ってみんな疲れてますからね。 「お疲れさま」っていうことばにはいろんな意味が入ってますよね。あなたがとてもよく頑張ったことを私は知っているっていう意味が一番多いのかな、私が使うときは。 成果がどうであれ、そこにたどりつくまでに緊張したり、慣れないことやったり、頑張ったり、ちょっと無理したりして…。なんだろうな… 自分を偽るわけではないんですけど、でも自分を小さい箱に閉じ込めたり、自分を必要以上に大きく見せたりっていうことをして、金曜日になったんだと思うんですよ、1週間。そこで「お疲れさま」って言って、シュっと自分のありのままのサイズに戻る、そういう呪文みたいになったらいいですね。 「ラジオ深夜便 インタビュー ここからアンコール ラジオパーソナリティー・コラムニスト ジェーン・スー」 6月1日(木)午前2時まで「NHKラジオ らじる★らじる」で聞き逃し配信中 https://www.nhk.or.jp/radio/player/ondemand.html?p=0324_03_3863478

ラジオの昼の顔に、そしてポッドキャストへ

繰り広げられるのは“無駄話”

「負けへんで」にこめた思い

“モヤモヤ”を言語化する

「背中は押しません」

50歳になったいま、考えること

女性の人生を取材して見えたこと

あなたに「おつかれさま」